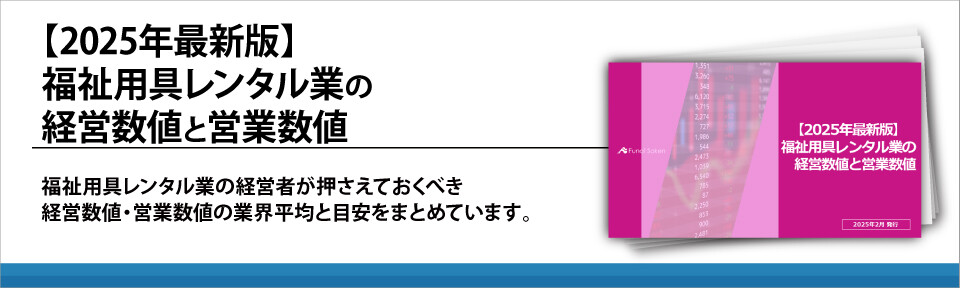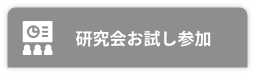- 2025.04.07
-
最新情報・トピックス
福祉用具レンタル業 粗利の「1%」にこだわろう!
INDEX -
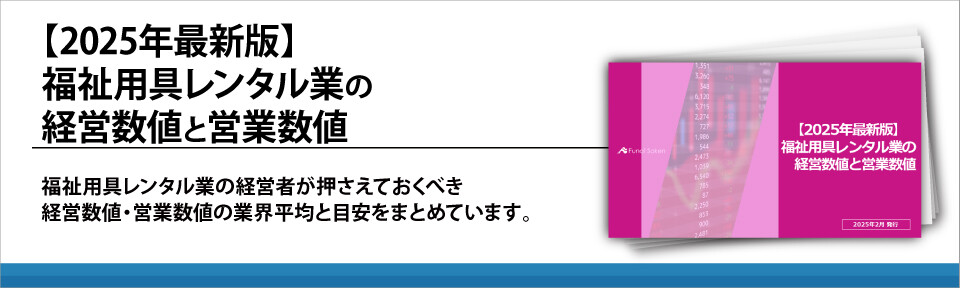
みなさんの会社ではどのくらい粗利率を上げることに目を向けているでしょうか。
ある会社は利用者数の増加に伴ってどんどん戦力を増強し、順調に企業として成長、経営者もどこか余裕を感じさせる雰囲気。
一方で、同じように利用者数は増えてもなんだかいつもカツカツ、人が増えれば増えるほど経営は苦しくなるばかり。
この差はどこからくるかというと、粗利率の「1%」にこだわるかどうかにあるといったらどうでしょうか。
今回は経営の根幹ともいえる粗利益についてみなさまと一緒に考えてみたいと思います。
ポイント1:成長投資の原資はレンタルの利益から生まれる
福祉用具レンタル事業というのはその事業特性から、ある程度の利用者数規模を超えると、それまでがまるでウソのように経営が安定してきます。
利用者数が数百名レベルだとまだ経営としてはなかなか安定してきません。
例えば、利用者数600名くらいだと年商は8,000万円~1億円くらい。粗利はだいたい4,500万円くらいでしょうか。
営業が3~4名、事務員さんも入れて6名くらいで運営しています。
社員1名につき年間700万円~800万円くらい必要になりますので、利益は出るか出ないかカツカツの状況になってしまいます。
利用者数が1,000名を超えると少し楽になってきます。
例えば、利用者数1,500名の会社だと年商は2億円~2.5億円くらい、粗利で1億円程度になってきます。
営業が7~8名、事務員さんも入れて10名くらいで運営しています。
同じく社員1名につき年間700万円~800万円くらいが販管費と想定すると、そこそこ利益が出るような状態になってくるでしょう。
利用者数が3,000名程度を超えてくるとかなり経営として安定してきます。
利用者数3,000名だと年商5億円、粗利で2.5億円と想定しましょう。
営業が15名、事務員さんやサポートスタッフさんも入れて20~25名と想定すると、販管費は1.6億円~2億円となります。
それだけの利益をそのまま出すか、将来の成長のための投資にお金を使うという会社も多いことでしょう。
そう考えると、経営として安定するかどうかの分水嶺はだいたい利用者数1,000名を超えるかどうかが最初のステップになりそうです。
同じ利用者数だったとしても、会社によって、社長によって、ものすごく余裕があるケースもあれば、なんだかいつまでもしんどそうなケースもあります。
余裕がある社長さんは本当に経営が楽しそうです。
日々の営業や運営は社員に任せて、常に先のことを考えています。
先のことを考えて組織をつくるとか、仕組みを考えるとか、新しい事業のことを構想するとか、頭の中は「やりたいこと」でいっぱいです。
もちろんお金にも余裕があるので、いろんなことに投資ができる状態です。
情報を集めるためにいろんなところに出かけていって、新しい人との出会いもいっぱいです。
みなさんの周りにも「あ、あの人のことかな。」と思い当たる方、いらっしゃいませんか?
そうした方、そうした会社はなぜそんなにも余裕があるのか。
その大きなポイントの一つが「粗利益」へのこだわりにあると思うのです。
しっかり粗利益を稼いでいる会社は余裕があり、善循環サイクルが回るようになっていく。
一方で、粗利益に無頓着な会社はなんだかいつもカツカツでちょっとしんどそう。
会社をいいサイクルにもっていきたければ「粗利益」にこだわること。
そんな目線をもってみてはいかがでしょうか。
みなさんの会社は、余裕がある状態ですか?いつも追い込まれている状態ですか?
ポイント2:卸レンタルでも粗利率にこだわった動き、できていますか?
前提として、ここでは自社レンタルではなく、卸レンタルの会社さんに焦点を当ててお話を進めていきたいと思います。
レンタルの粗利を上げようとしているかどうか。
あくまでも私の肌感覚ですが、常に仕入を見直して粗利率を上げようとされているのは全体の2割くらい。
残りの8割はレンタル粗利に対して何か策を講じているとは言い難い状態だと思います。
レンタル粗利を高めようと思うと、3つほど段階があるかなと思います。
一つ目の段階は、粗利率の高い商品を出すこと。
同じ「特殊寝台」でも商品によって粗利率が高いものもあれば、そうでないものもあると思います。
粗利に無頓着な会社は、
営業が出しやすいモノを出す。
あるいは、商品によっての粗利率がわからない。
そんな状態でしょう。
せっかく出すなら1ポイントでも2ポイントでも粗利率が高い商品を出すようにしているかどうか。
まずはここから見直しをしていくことだと思います。
注)
あくまでもお客様に適した商品の選定をして、その上で粗利率によって出す商品を変えていくというお話です。
お客様に必要か否か、適しているか否かをすっ飛ばして自社の利益を優先して考えるということではありません。
二つ目の段階は、粗利率の高い卸さんから仕入れること。
まったく同じ商品でも、どこの卸さんから仕入れるかによって粗利率は変わってくることでしょう。
ただ、そこに無頓着で現場任せにしていると、粗利率とは無関係に仕入れる卸さんを選んでしまうということになりかねません。
あそこの卸さんは無理を聞いてくれるから・・・
あそこの卸さんにお願いすると組配がラクになるから・・・
現場で優先されるのは、そうした基準で仕入先を選んでしまいがちになります。
そんなところも見ていくと粗利率は変わってくることでしょう。
三つ目の段階は、定期的に卸さんと交渉すること。
だいたい8割くらいの会社さんが「一度も卸さんと交渉したことがない。」と言ったら言い過ぎでしょうか。
利用者数が数百名の会社さんでも、ある卸さんへの月の発注が150万円とか200万円くらいあって、発注金額が伸びていっているのであれば十分に交渉の余地はあると思います。
交渉といっても一方的にこちらの立場だけで「とにかく安くしろ!」というのは下の下策です。
これからも伸びていくし、伸ばしていくという姿勢やプランを示した上で、そのために協力してほしいという思いを伝えていくと良いと思います。
「長年お世話になっている卸さんにそんなことを言うのは申し訳ない・・・?」
そんなことはありません。
卸さんもビジネスなら、こちらもビジネスです。
お互いに実績を伸ばして売上を伸ばしていく方が絶対にいい関係になると思います。
あとは、そうした交渉を定期的にし続けることでしょう。
一度交渉したからといって劇的に有利な仕入れ条件になるなどあり得ません。
3か月に一度とか、半年に一度とか、継続して話をしていくことでちょっとずつ条件が改善していくと捉えておくことだと思います。
売上の7割を占めるレンタル。
そのレンタル粗利を少しずつでも高めていくことで全体の粗利率が変わってきます。
ぜひレンタル粗利に着目して、利益を高める動きを取っていかれることをオススメいたします。
ポイント3:たかが「1%」そこにこだわる社長こそ成功を導く
福祉用具レンタルというのは、もともと高い粗利率に恵まれている事業構造です。
卸レンタルでも粗利率が50%近いというのは、他のビジネスと比べてはるかに高い利益率の業界だと思います。
ただそれだけに、そこに甘んじて利益率に対して無頓着でいるのか、はたまたストイックに0.5ポイントでも、1ポイントでも高める努力をしていくのか、最終的に会社の利益体質に大きな差になって出てくると思います。
冒頭にお話しした、どこか余裕のある会社さんは「1%」にこだわり、少しでも粗利率を高める動きをしています。
まだまだ小規模なうちからでも「1%」の粗利率にこだわる意識をもっておくと、やがて成長していったときに大きな差になります。
月次のレンタル売上が500万円であれば「1%」で5万円ですが、レンタル売上が3,000万円になると「1%」で30万円にもなります。
年間で360万円、人ひとり採用できるくらいのお金を生み出すことができるようになります。
絶えざる工夫と折衝によってたかが「1%」の利益をひねり出す会社は、結果的に投資資金を手にして常に先をみた成長投資をしていく「余裕のある会社」になります。
ぜひ、社長の仕事として「粗利率の改善」に目を向けてみてはいかがでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ビジネスモデル解説動画
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★住宅改修×福祉用具 セット提案モデルをわかりやすく解説
福祉用具レンタル業 なぜセット提案モデルは業績が上がるのか?
ビジネスモデル解説ムービーはコチラから!
https://youtu.be/-_8JNMWxZEw
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ビジネスモデル研究会情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★福祉用具レンタル事業者向け
「福祉用具&リフォーム経営研究会」
福祉用具レンタルと住宅改修をセットで提案することで、
業界3倍の獲得数を実現するビジネスモデル。
全国の会員企業で成功事例が続出中!
詳しくはコチラ↓
https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/fukushiyougu/027871
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 過去のメルマガバックナンバー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
何回読んでも、ためになる。
経営に迷った時の指標になる。
過去の成功事例バックナンバーはコチラ。
http://www.funaisoken.co.jp/site/column/column_mailmag1332.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 執筆者紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 船井総合研究所
リフォーム支援部
シニア経営コンサルタント
入江 貴司
【プロフィール】
シニア向けビジネスの立ち上げを専門に手がけるなかで、福祉用具レンタルと
シニアリフォームを掛け合わせた「セット提案モデル」を開発し業界に対する
専門コンサルティングを進める。
商圏内一番事業所に向けた戦略づくり、マーケティング・営業支援、組織体制
づくりなど業界企業のビジネスモデル化を強力に推進する。
⇒ 入江 貴司 への経営相談は、コチラまで
E-Mail:takashi_irie@funaisoken.co.jp