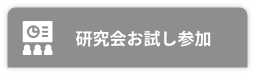- 2025.09.17
-
営業手法
福祉用具レンタル業 居宅内シェアの見極めと取るべきポジション
INDEX -
けっこう食い込めていると思っていたら、他社の方がダンゼン入り込んでいた・・・
開拓営業においてはどの程度切り込みができていて、
どれくらいシェアを取れているかの見極めが重要になってきます。
居宅内のシェアの見極めとそれに応じたポジションの取り方について考えていきたいと思います。
ポイント1:切り込みか、拡大か、維持・熟成か、シェアによって攻め方が変わる
ケアマネ営業をされているみなさんは無意識のうちに、それぞれの居宅によってアプローチの仕方を変えていることでしょう。
ある程度関係ができているところへはグイグイいく
まだまだ開拓途中のところは距離感を測りながら切り込みを狙う
そのような感じで無意識で対応やアプローチを変えているという方はいらっしゃると思います。
もしかして相手との関係性を考えずにアプローチしている・・・
なんてことはありませんよね!?
おそらく関係性ができていないのにグイグイいってしまうということはあまりないかもしれませんが、
すでに関係性ができて馴染み感がでてきているのに、いつまでも丁寧すぎる接し方をしているケースはあるかもしれません。
居宅の開拓を進めて、切り込みの段階から、拡大の段階へ、はたまた関係を維持しながら熟成させるという流れのなかで、
それぞれのフェーズによって攻め方は変わっていくと思います。
<切り込みフェーズ>
開拓初期の段階で「はじめまして」からはじまる
お互いによく知らないので、距離感を測りながら、接触頻度を高めて距離を詰める動きをする
<拡大フェーズ>
何度か依頼をもらってポツポツ実績も上がってきている
そのケアマネからリピートしてもらうとともに、他のケアマネにも伝播するよう拡大を狙う
<維持・熟成フェーズ>
十分に実績ができ、関係性も深くなっている
他社にスイッチされないように維持するとともに、より多面的な付き合いができるよう熟成を図る
狙う居宅が切り込みなのか、拡大なのか、はたまた維持・熟成なのか、感覚でわからなくもないですが、
なかにはある程度入り込めていると思っていたら、ぜんぜん切り込みもできていなかった・・・
というのは笑うに笑えません。
より客観的に、定量的に関係性を把握するには事業所シェアという概念で測るという手があります。
どのように事業所シェアを考えるのか?
続きのポイントでお伝えしてまいります。
ポイント2:居宅内でどのくらいシェアを取れている!?
介護サービス情報公表システムを検索すると、それぞれの居宅が、どの福祉用具貸与事業所を、どのくらいの割合で使っているか、
上位3つまで見ることができると思います。
シェアの高い会社さんであれば、そこに名前が出てくるかもしれませんが、
開拓の初期段階でぜんぜん使ってもらってなければ、名前すら載ってきません。
また公表されているシェアというのが正確なのかどうかという点もあると思います。
居宅によっては本当に正確に算出して申告しているところもあれば、
なかには回答された方の主観というところもあるのではないでしょうか。
そこで自社の居宅内シェアを算出するひとつの方法をご紹介したいと思います。
居宅/包括の事業所内シェア = 自社利用者数 ÷ 想定事業所福祉用具利用者数 × 100%
自社利用者数はカンタンにわかると思います。
その事業所から何人の利用者さんを依頼いただいているか、ちょっと調べればすぐにわかりますよね。
問題は、想定事業所福祉用具利用者数ですが、次のように想定するようにしています。
想定事業所福祉用具利用者数 = ケアマネ人数 × 平均担当件数(40) × 福祉用具利用率(30%)
例えば、3人ケアマネの居宅であれば、
想定事業所福祉用具利用者数 = 3人×40件×30% = 36人
そのうち、まだまだ開拓初期段階でようやく3人の利用者を依頼いただいているとすると、
事業所内シェア = 3人÷36人×100% = 8.3%
というようにシェアを算出することができます。
ケアマネ人数さえわかればシェアを推定することができますので、
ぜひみなさんの担当エリアでも各居宅/包括のシェアを算出してみていただければと思います。
ポイント3:居宅内シェアに応じた取るべきポジションとは
居宅/包括の事業所内シェアが算出できたとして、そこからどうすればいいのかという話になります。
| シェア | ランク | フェーズ |
| ~26% | Cランク | 切り込みフェーズ |
| 26~74% | Bランク | 拡大フェーズ |
| 75%~ | Aランク | 維持・熟成フェーズ |
シェアによっておおよそ上記のように考えると良いと思います。
26%、、、つまり1/4程度のシェアしか取れていない段階はとにかく関係性を築くべく「切り込み」をしていくということになります。
しっかりと接触頻度を保ち、上位の貸与事業所にスキがあればいつでも声をかけてもらえるよう「便利な」ポジションを取っていきます。
26%~74%、、、シェアが上がってきて一定の関係が築けてきたら、そこからの「拡大」を狙っていきます。
より一層のリピート依頼をもらえるように利用者対応力と報告・連絡・相談をマメに行う。
上位の貸与事業所との差別化を図り、事業所内で評判が起きて他のケアマネに人づてで連鎖が起こるように武器を磨いていく。
75%以上、、、かなり独占的なポジションです。
油断して他の事業所にスイッチされないように「維持」しながら、一番手ならではの動きをしていくようにします。
信頼できる事業所にしか任せられないような利用者の依頼を受けたり、珍しいケースに一緒に対応したりして「熟成」を図っていきます。
開拓が進むにつれて事業所内シェアが上がり、取るべきポジションが変わっていく。
そんな様子を今回のコラムではお伝えしてきました。
すでに距離感が近いポジションが確保できているのも良いですが、
開拓フェーズで切り込みをしていくのもとても面白いものだと思います。
福祉用具営業として実力がある方にはぜひ、どんどん開拓に回っていただきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ビジネスモデル解説動画
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★住宅改修×福祉用具 セット提案モデルをわかりやすく解説
福祉用具レンタル業 なぜセット提案モデルは業績が上がるのか?
ビジネスモデル解説ムービーはコチラから!
https://youtu.be/-_8JNMWxZEw
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ビジネスモデル研究会情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★福祉用具レンタル事業者向け
「福祉用具&リフォーム経営研究会」
福祉用具レンタルと住宅改修をセットで提案することで、
業界3倍の獲得数を実現するビジネスモデル。
全国の会員企業で成功事例が続出中!
詳しくはコチラ↓
https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/fukushiyougu/027871
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 過去のメルマガバックナンバー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
何回読んでも、ためになる。
経営に迷った時の指標になる。
過去の成功事例バックナンバーはコチラ。
http://www.funaisoken.co.jp/site/column/column_mailmag1332.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 執筆者紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社 船井総合研究所
リフォーム支援部
シニア経営コンサルタント
入江 貴司
【プロフィール】
シニア向けビジネスの立ち上げを専門に手がけるなかで、福祉用具レンタルと
シニアリフォームを掛け合わせた「セット提案モデル」を開発し業界に対する
専門コンサルティングを進める。
商圏内一番事業所に向けた戦略づくり、マーケティング・営業支援、組織体制
づくりなど業界企業のビジネスモデル化を強力に推進する。
⇒ 入江 貴司 への経営相談は、コチラまで
E-Mail:takashi_irie@funaisoken.co.jp